あなたも経済を支える一員なのです。良い買い物をすることで、世の中にいい商品が広がる手伝いをすることができます。
本書より
本書は、物を買う、クレジットカードを使う、納税という身近な行為についての経済的な深い意味について分かりやすく解説してくれています。
本書の中で共感し、豊かな人生を送るためため、みなさんに伝えたいことを私の考えも交えて、まとめました。
「経済とか難しいこと興味ない」という人も、きっと面白いと感じるはずです!

商品を買うとき、それをつくっている企業や人を応援している!
自分の買い物には、大事な意味があることに気付くところからスタートです
商品を買うことは「企業に投票すること」!

皆さんが買い物をして払ったお金がどうなるか、想像したことはありますか?
そのお金は、その商品に関係している人たちに分配されていきます。
たとえば、皆さんが服を買えば、その代金は、店員、メーカー、原料メーカー、運送屋さんと多くの人に分けられます。
皆さんが買い物をすることで、世の中の人たちの生活を支えていることになります。
その人たちも得られたお金で買い物をし、また別の人たちに分配されていきます。
リーマンショック、コロナショックと最近不景気続きですが、そんなときこそ、本当に欲しいものを吟味して買ってみましょう。
皆さんの厳しい目が、ダメな企業を追い出し、本当に欲しいものを提供できる良い企業を発展させるからです。
これを著者は「経済における投票活動」と呼んでいます。

株を買うことだけではなく、日常の買い物でも、自分が好きな企業を応援できるのですね
政治の世界では、有権者の支持を受けた人が当選し、そうでない人は落選します。
経済の世界でも同じようなことが起こっています。
ブランド品の中には、創業100年以上というものがあります。
ロレックス1905年~、シャネル1909年~、グッチ1921年~等
ブランドを持つ企業は、100年以上努力して信頼を築き、不景気の度に消費者に選ばれてきた、といえます。
なので、そのようなブランド品を買うことは、良い買い物といえるかもしれません。
ただし、他の人が持っているから私も欲しい、のような他者の価値観で購入するのは皆さんの「一票」を無駄にしています。
なぜなら、自分の価値観に合っていると思って購入していないからです。

物を買うとき、「あの人と比べて」とか「世間的には」という視点はいらない、ということです
自分の買い物が、他の人の生活を支え、自分の好きな商品を売る企業を残すことにつながる、そう思って買い物をすると、雑なお金の使い方はできないですね。
カードでの買い物も借金?

クレジットカードの使い方は、義務教育でやらないし、特に日常の1つ1つの買い物は金額が小さいので、「借金」の感覚はないかもしれません。
カードで買い物をすると、1か月遅れくらいで請求書が来ます。
この間何が起こっているか知っている人は意外と少ないのでは?
商品を購入すると、まずカード会社から商品を買ったお店にお金が振り込まれます。
この時点で、皆さんはカード会社からお金を借りた状態になります。
そして、この借金を後からカード会社に返済することになります。
皆さんがカードで買い物をするときに、サインをすることもあると思います。
これは「『確かにこの金額の借金をしました』という借用書にサインをすることと同じです。」と著者は言います。
しかし、実態「借金」というにはあまりに手軽ですね。
サインするだけで、簡単に欲しいものが手に入るのですから、錯覚を起こす人も多いです。

私も、買ったときは借金の感覚はないです
お金を使った感覚すらないかも
しかし、当然ですが、毎月しっかり口座から引き落としがあります(泣)
最悪「リボ払い」という割高な手数料を延々支払うことになる借金地獄への片道切符を握らされます。
特にカード会社によっては、「月々の支払額が一定です」や「リボ払いで大量ポイント進呈」など甘い罠を撒いて、リボ払いを進めてきます。
リボという可愛い名前に騙されず、大事なお金を守りましょう。
リボではなく、「支払い上手」とか、「支払い調整」とか名前を変えてお勧めしてくる場合もあるようです。
できる・できない場合がありますが、リボ払いができないようカード会社に連絡する、もしくは設定するのが安全です。

楽天カードはできないみたいです
三井住友カード(NL)は、できるようです
(楽天証券やSBI証券のクレジットカード積立で利用できるカードです)
まず、カードの利用は、「一括支払い」一択です。
当然ですが、預金口座に入っているお金以上のものは買えないことは、忘れないでおきたいですね。
税金を払っているあなたは「タックスペイヤー」です

人は、お金を自分のために使うだけで経済を支えています。
しかし、個人だけでは賄いきれないものも当然存在します。
例えば、町の治安を守る警察官や火事を消化する消防士を個人で雇うことはできません。
みんなが使う道路をつくったり、メンテナンスをしたりするのも個人ではできません。
みんなでお金を出し合う必要があります。このお金が「税金」です。
つまり、税金の目的は、みんなからお金を出し合って暮らしやすくすることです。
この税金の使い道を考えるのが、みんなの代表「政治家」ですね。
まとめると、働いて得られた貴重なお金から、税金を支払い、その税金の使い道を考えるのが政治家ということです。
そう考えると、「自分のお財布から出ている税金の使い道は、税金の支払者「タックスペイヤー」として目を光らせるのは当然です」、と著者は言います。

税金をたくさん払っていようと、少なく払っていようと、同じ公共サービスを受けられるのは良いことだと思います
税金の使い方で自分の考えと違う人をみすみす当選させてはいないでしょうか。
投票に行ったからといって必ずしも、自分が入れた人が当選するとは限りません。
しかし、投票しないことには、可能性も0です。
良い企業が残るのに必要なものは、「経済活動における投票行動」という買い物でした。
税金の良い使い方については、「本来の投票行動」が求められます。

良い人がいなければ、ましな人に入れるとか、白紙で意思を突きつけることはできます
豊かな人生を送るために。「人生のリストラ」
「リストラ」=「人員削減」、「首切り」という悪いイメージを思っている人は多いと思います。
しかし、本来のリストラは、アメリカの経済戦略用語「restructuring」からきたもので、「再構築する」という意味です。
つまり、仕事のやり方を再構築する(抜本的に見直す)という意味で、人を削るだけがリストラではありません。

リストラにポジティブな意味があったのは意外でした!
なので、「人生のリストラ」は「自分の人生を振り返って、変える必要がある部分を変えていく」ということ、と著者は言います。
例えば、皆さんは、自分の本当に満足できるものを買うことで、世の中をより良い方向に回すことができます。
同じように、自分の仕事によって、誰かに喜ばれるようなものを生み出しているのであれば、皆さんの収入は、良いお金の使われ方を経て、皆さんのもとに来たということになります。
反対に、人を騙すことをして得られたお金は、そのお金を払った人を満足させていないため、良くないお金の使われ方をしたということになります。
仕事は基本的に楽しくやりがいのあるもののはずです。

仕事は、1日の大半の時間を占めるもの
ここが苦痛だとしたら、相当しんどいですね。。
しかし、意外と多くの人が、「何か違う」ともやもやとした気持ちを抱えながら、なんとなく毎日を過ごしています。
「会社行きたくない」、「でも行かないと生活ができない」
とりあえず続けていれば、毎月給料は振り込まれるし、さらにボーナスが貰えればラッキー。
「いつかやろう」と、やりたいことをやらずに妥協し続けていたら、いつの間にか人生終わっていました。
これが1番もったいないことです。
お金の無駄どころか、人生の後悔につながることもあります。
今そんな状態だと気付いたら、「人生のリストラ」で転職活動をしてみたり、副業をしてみたり、小さくても自分に興味があることをやってみたりしてはいかがでしょうか。

1日30分だけ、そのための時間をつくることから、始めましょう
毎日の小さな1歩の積み重ねは、1年後に変化を感じられるはずです
まとめ
この記事のまとめです。
- 買い物は、その商品をつくる企業への投票行為
- クレジットカードを使う=借金をする
- 税金の良い使い方は、本来の投票行為が求められる
- 定期的な「人生のリストラ」で豊かな人生を送ろう
何にお金を使うかで、その人の人となりが見えてきそうですね。
本書の中では、「銀行から借金すると信用を得られる」など、私としては共感できない部分もあります。
安定した収入が必ずしも保証されない今は、借金を返せなくなるリスクを抱えるし、自由な人生を生きる上でやはり足かせになるのでは、という考えからです。
それを差し引いても、本書は経済の基本的な知識を生活に密着させて、「経済オンチ」の私にもわかるように解説してくれています。

文字は大きめで、絵も多く、著者の池上さんの優しい語り口なので、読み易いと思いますよ


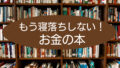
コメント